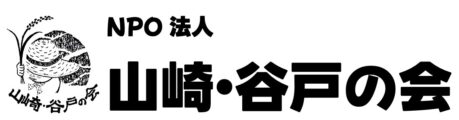1月から2月の谷戸の自然の様子(2025年3月・会報126号)
正月が過ぎて寒波が押し寄せ、北日本は大雪になりました。その影響か、冬鳥の種類と数が増えました。アオジの数が多くなり、カシラダカや
シロハラなどの冬鳥が例年より遅れてやってきました。
タシギやトラツグミ(妖怪ヌエの正体、口笛のような鳴き声で鳴き、昔は妖怪の鳴き声と恐れられていた)のようにやや珍しい野鳥もきています。2月6日からアカガエルの産卵が始まっています。2月13日は
アカガエルの鳴き声でにぎやかでした。
●「神奈川県内の自然の変化と気候変動ワークショップ」に参加して 1月30日横浜
当会と関わりのある団体が主催しているので参加しました。東京都市大学では、全国レベルでデータを収集していますが、それに協力する形で、日本自然保護協会の里地調査から得られたデータが発表されました。事務局のような形で県の環境科学センターの職員も来ていました。今回は、湘南地域の自然系の市民団体から現場の声を集めるのが目的です。温暖化による南方系の昆虫の増加、海藻の減少などの声が上がりました。さらに温暖化による豪雨の増加で、水路の被害が出ていることも報告され、今後は、田んぼや水路の手入れが難しくなると予想されます。私からは、2023年頃から、アマガエルやウマオイ、クモ類など一部の生きものが急減していることを発言しました。参加者の中には行政(小田原市)の方もいて、職員自らが市内の生きものの分布を把握しようと本気で取り組んでいる姿に驚かされました。日本自然保護協会からは、ノウサギ、セグロセキレイ、ヘイケボタル、
イチモンジセリ(チョウ)の全国的な減少傾向が指摘されました。日頃谷戸で実感していることが裏付けられたと納得しました。また当会のカヤネズミの保護事例(公園協会と協働し、野外体験広場の一部に草を刈り残してもらっていること)も紹介されました。身近な生きものを通じて環境問題を考える取り組みは評価できると思いますが、温暖化だけでなく化学物質の蓄積なども含め、複合的な視野が欲しいと考えます。今までの環境問題は、開発や里山の荒廃など目に見える変化との闘いでしたが、これからは見えない何かに包囲されるように環境が劣化していくのでしょう。気が付いたら、おなじみの生きものが消えていた。そんなことにならないように、谷戸の生きものを見つめていきたいです。
11月から12月の谷戸の自然の様子(2025年1月・会報125号)
例年冬鳥がやってくる季節ですが、今年は種類も数も少ないです。湿地にたくさんやってくるアオジが少ないほか、カシラダカなど冬に来る小鳥が来ません。北日本の雪で1月頃に増えてくることを期待しています。夏の猛暑の影響なのか、モミジの葉先が枯れてしまう現象が起きています。11月25日の夜に季節外れの豪雨が降り、クモの巣がたたき落されたらしく一斉になくなってしまいました。この日を境に虫の世界は冬を迎えた感じです。12月初めにカヤネズミの巣の調査をしました。今年は調査日が一カ月ほど遅れたためか巣が見つかりませんでした。巣が少ない年回りということも
あるかもしれませんが、来年はどうなるでしょうか。
●谷戸の生きものを守るために1 新しい試み
谷戸に昔からある田畑や雑木林を、なるべく昔ながらの方法で続けることが、生きものを守る基本です。生態系保全班や植物育成班では、田畑の周辺にあって手入れが届きにくい水路や湿地の環境維持作業をしてきました。ところが、前号で書かせてもらったように、環境は変わらないのに、一部の生きものが減ってきています。従来の里山管理だけでなく、新しい方法が求められている時期なのかもしれません。これには成功事例もあり、アカガエルの卵を移動してネットをかけて保護することで成果を上げつつあります。生態系保全班のメンバーの中にも、積極的に新しい方法を取り入れてはどうかという機運が高まり、虫の越冬場所や繁殖場所を人工的に提供する試みを始めました。「インセクトホテル」
と称し、近年話題になっている方法です。これは昔の里山にはどこにもあった、古い道具置き場や古民家を様々な生きものが利用していたのを再現する意味があります。建物の隙間や穴が多くの生きものの棲み処になっていたのですが、現代の谷戸にある建物やスチール製の物置ではあまり棲めません。「インセクトホテル」を本田の近くに設置するという案もありましたが、すでに道具置き場があるので、隣接地に設置するより、道具置き場や建物から遠い小段谷戸に置くことになりました。もし「インセクトホテル」の効果が確認できれば、来園者への啓発材料にもなるのではないかという意見もあります。今まで、生態系保全班では谷戸になかったもの設置する場合、アカガエルのネットのように、数年間の経過観察と必要性を確認しながら実施してきたつもりです。今回は設置が先行しましたが、しっかりと経過観察をしながら効果を確かめたいと思います。
変わりゆく自然(2024年11月・会報124号)
鎌倉は今年も台風が来ませんでしたが、全国的には能登の大雨、宮崎の台風など天災が多発しました。残暑が厳しく秋らしい日は少なかったです。夏日の翌日は10度以上も下がって肌寒くなったり、突然大雨が降ったり、不安定な気候でした。いつまでも秋らしくならないので、秋の花が咲くのが半月以上遅れ、ススキやオギの穂が10月になってやっと出てきました。
●急に減ってきた谷戸の生きもの
昨年から今年にかけ、一部の生きものが急に減りました。今の時点で感じていることを書きます。谷戸の植物はあまり変わらないのに、野鳥や昆虫が減少しているのはなぜでしょうか。ホタルなどあまり減少していない昆虫もありますが、以下の生きものは昨年から今年にかけて、おそらく5分の1以下に一気に減少してきた種類です。
シオヤトンボは、シオカラトンボによく似た、春に田んぼで見られるトンボです。山崎の谷戸にはシオカラトンボより多くいましたが、昨年あたりから減少が目立ちます。シオカラトンボはまだ多いのに、なぜシオヤトンボだけが減ったのでしょうか。アマガエルは、ホタルの観察会の時、田んぼでうるさいくらい鳴きますが、昨年あたりからあまり聞かなくなりました。ウマオイは、夏の夜「スイッチョン」と鳴くキリギリスの一種で、鎌倉に住む人は知っている人が多いでしょう。昨年から急に減り始め、今年の鳴く虫観察会では一匹の鳴き声を聞いただけでした。かつては5m間隔で鳴いていたくらい多かった虫です。同様に、アシ原に住むヒメギス
という黒いキリギリスもほとんど見なくなりました。湿地の環境はそのまま残っていてもそこに住む虫はいなくなっているのです。また、クルマバッタという畑の土手で見かけたバッタや、散策路沿いに多かったハエトリグモの仲間も見かけなくなりました。その他、10年以上前からですが、カタツムリが少なくなったのはみなが感じていることでしょう。まるで歯が一本ずつ抜け落ちていくように、生態系を支えていた生きものが姿を消しています。やがてこれが当たり前になり、豊かな里山は忘れられていくのでしょう。だからこそ、今まで通りに谷戸の活動を続けていくことが大切になったと感じます。なぜなら、環境(植物)を従来通りに保全しても、生きものが消えていくことが証明され、環境問題を根底から考え直すきっかけになるからです。
変わりゆく自然(2024年9月・会報123号)
今年は梅雨が短く、7月上旬から8月末まで連日猛暑が続いています。県内各地で突発的な豪雨に見舞われましたが、鎌倉だけは雨が降らず、水路も水路も田んぼも湿地復元した場所も水不足に悩まされました。晴天が恨めしい毎日でした。高温と水不足のせいか秋の野草があまり咲きません。梅雨時に草刈りした場所も草の再生が悪いです。ヤマユリの球根を大量に盗んだ人がおり、田んぼの山側の散策路に掘った跡が何か所もありました。毎月野草調査を続けているので、悪事はすぐに露見します。気温が高いわりには、セミやコオロギの初鳴きは例年通りの時期でした。高温のせいなのか、セミやチョウが少ないようです。あまりの暑さに日中は昆虫の活動が鈍っているようでした。今年はカが少ないという声を聞きますが、カのような微小な昆虫が減ったことが昆虫や野鳥にまで影響を及ぼしていると推定しています。ツバメ、コウモリ、アマガエル、トンボ、クモ、キリギリス、カマキリなどカを食べている生きものが減っているようです。それでもカネコトタテグモという珍しいクモが撮影されるなど、谷戸には都市部にないよい環境が残されていることがわかります。
●田んぼの生きもの今昔3
8月末になると、今までは防鳥ネットを張りましたが、最近はネットなしでも被害がないようです。スズメが来なくなったからです。かつては大群が田んぼを取り囲み、9月はスズメの鳴き声でうるさいくらいでした。スズメの減少は全国的に話題になっています。20年くらい前までは、稲刈りをするとカヤネズミの巣が見つかったものですが今はありません。周辺の湿地では今も見つかりますが、田んぼで巣が見られなくなったのは不思議です。田んぼには、稲の間に網を張ってトンボを食べるナガコガネグモという大きなクモがいますが、近年は数が減っています。昨年は田んぼに多いチョウセンカマキリが少ないのに気づきました。稲刈りや、稲を束ねる作業の時に見つかるので探してみてください。秋は赤トンボ(アキアカネ)が田んぼで産卵し、モズが田んぼの周辺で鳴き始める季節です。
今年の秋も健在でしょうか?生きものの増減は年により差があるので、5年くらい観察しないと本当のことはわかりません。これからも谷戸の生きものを見つめていきたいと思います。
変わりゆく自然(2024年7月・会報122号)
梅雨入りが大幅に遅れ、6月下旬に梅雨入りしました。ゲンジボタルが6月上旬にピークを迎え、6月半ばには早くもヘイケボタルが数多く見られました。例年より10日早いペースでした。ゲンジボタルの数は6月7日に約100匹見られたので多めだったようです。オタマジャクシは小段谷戸で順調に育ち、ネットをかけた場所以外でも、アマガエルやシュレーゲルアオガエルのオタマジャクシが育っています。心配なのは、シオヤトンボが今まで経験しなかったほど少なかったことです。原因は不明です。シオカラトンボも減っていますが、元の数が多いので、それほどではありません。今年の初夏は、ツバメ、スズメ、ムクドリがとても少なく、ホオジロも見かけませんでした。里山と縁の深い野鳥が減っているのは、周辺の環境変化、田畑や空き地の減少、瓦屋根の減少などが原因でしょう。
●田んぼの生きもの今昔2
昔と今の大きな違いは、多くの人が入るようになったこと、水が少なくなったことでしょう。もとはSさんとTさんの2名が所有していた田んぼで、それぞれ農法も違っていたようです。昔ほどではありませんが、今でも区画ごとに生きものの違いがあります。山際にある「細田」「深田」は「しぼり水」だけの田んぼなので、ホタルやオタマジャクシがよく育ちます。畑よりにある「大田」「小田」は乾きやすいので、卵で越冬する赤トンボの幼虫によい環境です。真ん中にある「仲通り」といわれる数枚の田んぼにはミズオオバコという特殊な草が生えます。「池山田」と呼ばれる上流部の田んぼは、水路に近いので、水路と田んぼを往来するホトケドジョウの稚魚が育つ場所です。畔が昔のままに維持されている限り、区画ごとの特徴を守れると思います。谷戸の田んぼは、水路だけではなく、畔から目に見えない「しぼり水(湧水)」が湧き出して水を供給しています。ヘイケボタルの幼虫は、年間を通じて温度差が少ない「しぼり水」で育っているようです。田んぼのヘイケボタルが1980年代に比べて大幅に減少したのは、「しぼり水」が減ったのと関係がありそうです。1995年ごろ、地主さんが「谷戸の水が少なくなった」と首をかしげておられたのを覚えています。1980年代は「細田」の上にある竹筒から「しぼり水」が流れ落ちていたことを記憶されている方もいるでしょう。夏に田んぼに入ると、冷たく感じる地点があります。そこが「しぼり水」の出ている場所です。田の草をとりながら「しぼり水」を探してみませんか。
変わりゆく自然(2024年5月・会報121号)
3月前半は初夏のような陽気もありましたが、3月の後半から冬のような寒さの日がありました。当初の予想に反して、例年よりも桜の開花が遅れる結果となりました。アカガエルの卵を保護するようになってから3年、今年は昨年を上回る350個を記録し、10年前とほぼ同じ数に回復しました。ところが、アカガエルやヒキガエルの卵まで、根こそぎ持ち去られる事件が発生しました。田んぼには犯人の足跡がついていました。ヒキガエルは2年ぶりにやっと産んだ卵だったので、今後の存続が心配です。アカガエルはネットで保護した場所は無事でした。市内の野村総合研究所跡地の池、広町緑地でも同じ事件が起きており、大量の卵が一気に盗まれていることから、組織的なプロの仕業ではないかと感じます。
●田んぼの生きもの今昔
当会が谷戸の田んぼに関わるようになってから、40年近くがたちました。環境も生きものも変わり、人も代わりました。特にここ数年は、生態系の変化を感じますので、昔の様子を書いておきたいと思います。
桜が散る頃になると、シュレーゲルアオガエルがにぎやかに鳴き、田んぼにはシオカラトンボによく似たシオヤトンボが飛びはじめ、畔にはタンポポのようなオオジシバリの花が咲き始めます。春だけに見られるシオヤトンボが多いのは山崎の谷戸の田んぼの特徴でしょう。また、田んぼに亀(クサガメ)が棲みついており、作業中に見つかることもあります。以前、田んぼ班の人たちが、甲羅に印(甲羅のふちに切り込みが入れてある)をつけて一匹ずつ身体測定をして記録していました。その台帳が今でもありますので、興味のある方はぜひご覧になってください。冬の間も水がある田んぼであること、畔つけなど昔通りの作業がこれらの生きものを守っています。一方、大きく変わってきたのは、田んぼの水の中の生きものです。昔は田うないをしていると、足元にたくさんのアカガエルのオタマジャクシが泳いでいました。水生昆虫も多く、田植え前の田んぼは水族館のようでした。今は昔にくらべると寂しくなってきましたが、その原因の一つに、野鳥の習性が変わってきたことがあげられます。アオサギという今までいなかった大型の野鳥が田んぼで生きものを食べるようになったり、カルガモが田んぼの生きものを食べつくしてしまうからです。カルガモは昔からいましたが、今ほどは谷戸に依存していなかったと思います。昔は谷戸周辺の住宅地に田んぼが残っていましたが、それらがなくなってしまったので、谷戸の田んぼに頼らざる得ないのでしょう。アオサギやカルガモの被害は他の里山でも報告されています。